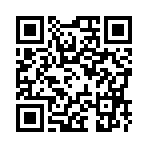2010年06月18日
文化で語るラグビー『Lowの精神』

ラグビーというスポーツは、プレーが先で、ルールが後からついてきたスポーツです。
ラグビーの前身のフットボールは「一点先取で即、勝利」であったので
どちらかが得点をした時点でゲームは終了だったそうです。
したがって、この面白いフットボールをできるだけ「長く楽しむ」ように様々な事が考え出され、
ルール化されていった。
この「長く面白くやる」というのが根本にあるため、現在でもラグビーという競技は
「つまらなくなったら(危険ならば)ルールを変える」のです。
よく「ラグビーはルールがころころ変わり、わかりにくい」という声がありますが、
「面白くなければルールを変えること」こそがラグビーのアイデンティティーなのです。
このルールを変える上での不文律というものがラグビーには存在します。
例えば
「ボールの争奪が始まったら、ボールの進行を妨げるような行為はしてはならない。」
という不文律があって、その上にルールがある。
したがって、ラグビーでは「ルールに絶対権はなく、判定はレフリーの裁量に任される。」
それがラグビーの本質です。
「レフリー」という言葉の語源は「ゆだねる」ということです。
アンパイア(事実を判断する人)とは根本的に違う。
レフリーにゲームを一任している、それが「Lawの精神」なのです。
ラグビーでは「ルール(Rule、規則)」ではなく「ロゥ(Low、法律)」なのです。
法律なので守って当たり前。
それじゃなきゃ、レフリー1人で30人の屈強な大男を相手にできませんよね。
Posted by hamakorfc at 08:57│Comments(0)
│管理人のつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。