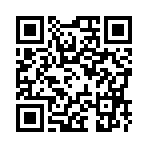2010年06月17日
文化で語るラグビー『キャプテンシー』
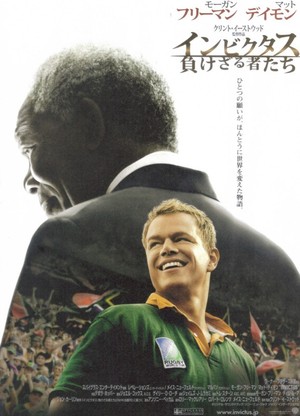
ラグビーほどキャプテンシーを重要視するスポーツはないと思う。
試合前日の練習は「Captain'S Run」とよばれ、監督・コーチは練習に一切関与せず
練習はキャプテンとバイスキャプテンによって運営される。
そして、キャプテンがこれでゲームに望めると判断した時点で練習が終わる。
日本でも部歌などは、必ず最初はキャプテンの独唱から始まる。
また大学ラグビーではその年々の代をキャプテンの名前にしたがって「〇〇組」と呼ぶ。
よく一般的に、
「ラグビーはゲーム中に監督・コーチからは指示ができないためにキャプテンが重要なのだ。」
という説明がされるが、歴史的背景から考えるとこの説明は必ずしも正しいとはいえない。
ラグビーの前身のフットボールでは、ゲームを進める上で不都合なことが起こったら
その都度、双方のキャプテン同士が話し合いで解決していったそうだ。
選手たちはキャプテンを中心に、選手だけでゲーム中の様々な問題に対処しなければならなかった。
したがって、リーダーの能力が大きな鍵となった。
これが、ラグビーというスポーツに「キャプテンシー」を重要視する文化が育った背景ではなかろうか。
Posted by hamakorfc at 08:16│Comments(0)
│管理人のつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。