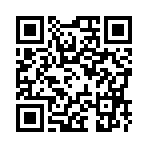2012年12月24日
「Who」より「Why」
今日の練習試合は見に行けませんでした・・・。
行きたかったですが、残念です。
今日の対戦相手はさすがに強かったようですね。
帰ってきた子供のご機嫌を窺いながら(笑)、ふっと思ったことをまたもやつらつらと・・・・。
5W1Hという言葉があります。
ご存じだとは思いますが、説明をさせていただくと、
「いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)」
という、物事を把握するための6つのファクターを5W1Hと言います。
私は仕事上、現場から報告を受ける事が多いのですが、受けているうちに気付いたことがあります。
それは何かと言うと、報告をする人は皆、「Who(だれが)」にこだわる事。
仕事の性質から、良い事が報告されることは残念ながら少なく(勿論現場ではたくさん良い事も起っていますが)、ミスや失敗、クレームなどの報告が大半です。
その時、一番現場の皆が報告に力を入れるファクターが、「Who(だれが)」そのミスを犯したか、なのです。
しかしながら、報告を受けた後どうしたら同じ失敗を繰り返さないようにするか改善策を考えなくてはいけない私としては、正直、誰がミスを犯したかというのは、どうでもいいとまでは言いませんが、ぶっちゃけ割とどうでもいいです。
もっとも重視するのは、「Why(なぜ)」と「How(どのように)」。
それは何故か。
ミスは誰にでも起こる可能性があります。たとえば今回、Aという人がミスを犯したとして、A以外の人が絶対ミスを犯さないかというと、そんなことはありません。
今回ミスを犯したAを除いて仕事のチームを編成しなおしたとして、たぶんかなりの確率で別の人が同じミスを犯すでしょう。
だから、「Who」にこだわるのはとてもナンセンスな事なのです。
そして、「なぜ」「どのように」ミスが起きたかを分析して対策を立てなければ、失敗の無限ループは続きます。
理論としてはそうなのですが、感情としては「だれが」ミスを犯したかを確認した時点で、8割方解決したような気になってしまうものです。
「Aが失敗したから」「Aがミスしなければうまく行った」と考えて、結論付けてしまいがちです。
それでは、チームの成長は到底望めません。
そうではなく、「誰にでも起こりうる事」として一人一人が考えて行かなくてはいけませんが、これまた感情として「自分がミスしたわけじゃないのに何で反省しなくちゃいけないんだ」と思ってしまいます。
私自身、まだまだ仕事の上では未熟ですから、それをスタッフに納得してもらうのにとても骨を折ります。
一方、浜工ラグビー部で、失敗した誰かを責めるシーンを私は一度も見た事はありません。むしろ、励ますシーンしか見た事がないです。本当にいいチームだなと思います。
でも、逆もまた同じなんです。
自分がミスをして、「おれのせいだ。おれのミスせいで負けたんだ。」とだけ思ってしまったら、そこで成長は止まってしまいます。
ここでも、「だれ」ではなく、「なぜ」を考えていきましょう。
100%ミスをしない、なんてことは誰にもできません。
でも、限りなくミスを0(ゼロ)に近づける事は、誰にでもできるんです。
新人戦はまだまだ続きます。
1試合1試合から何かを掴んでいきましょう!
行きたかったですが、残念です。
今日の対戦相手はさすがに強かったようですね。
帰ってきた子供のご機嫌を窺いながら(笑)、ふっと思ったことをまたもやつらつらと・・・・。
5W1Hという言葉があります。
ご存じだとは思いますが、説明をさせていただくと、
「いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How)」
という、物事を把握するための6つのファクターを5W1Hと言います。
私は仕事上、現場から報告を受ける事が多いのですが、受けているうちに気付いたことがあります。
それは何かと言うと、報告をする人は皆、「Who(だれが)」にこだわる事。
仕事の性質から、良い事が報告されることは残念ながら少なく(勿論現場ではたくさん良い事も起っていますが)、ミスや失敗、クレームなどの報告が大半です。
その時、一番現場の皆が報告に力を入れるファクターが、「Who(だれが)」そのミスを犯したか、なのです。
しかしながら、報告を受けた後どうしたら同じ失敗を繰り返さないようにするか改善策を考えなくてはいけない私としては、正直、誰がミスを犯したかというのは、どうでもいいとまでは言いませんが、ぶっちゃけ割とどうでもいいです。
もっとも重視するのは、「Why(なぜ)」と「How(どのように)」。
それは何故か。
ミスは誰にでも起こる可能性があります。たとえば今回、Aという人がミスを犯したとして、A以外の人が絶対ミスを犯さないかというと、そんなことはありません。
今回ミスを犯したAを除いて仕事のチームを編成しなおしたとして、たぶんかなりの確率で別の人が同じミスを犯すでしょう。
だから、「Who」にこだわるのはとてもナンセンスな事なのです。
そして、「なぜ」「どのように」ミスが起きたかを分析して対策を立てなければ、失敗の無限ループは続きます。
理論としてはそうなのですが、感情としては「だれが」ミスを犯したかを確認した時点で、8割方解決したような気になってしまうものです。
「Aが失敗したから」「Aがミスしなければうまく行った」と考えて、結論付けてしまいがちです。
それでは、チームの成長は到底望めません。
そうではなく、「誰にでも起こりうる事」として一人一人が考えて行かなくてはいけませんが、これまた感情として「自分がミスしたわけじゃないのに何で反省しなくちゃいけないんだ」と思ってしまいます。
私自身、まだまだ仕事の上では未熟ですから、それをスタッフに納得してもらうのにとても骨を折ります。
一方、浜工ラグビー部で、失敗した誰かを責めるシーンを私は一度も見た事はありません。むしろ、励ますシーンしか見た事がないです。本当にいいチームだなと思います。
でも、逆もまた同じなんです。
自分がミスをして、「おれのせいだ。おれのミスせいで負けたんだ。」とだけ思ってしまったら、そこで成長は止まってしまいます。
ここでも、「だれ」ではなく、「なぜ」を考えていきましょう。
100%ミスをしない、なんてことは誰にもできません。
でも、限りなくミスを0(ゼロ)に近づける事は、誰にでもできるんです。
新人戦はまだまだ続きます。
1試合1試合から何かを掴んでいきましょう!
Posted by hamakorfc at 18:26│Comments(0)
│よろづ事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。