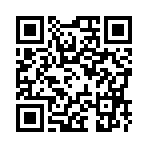2011年01月25日
意味のある練習を
皆さんは日頃から考えながら練習していますか?
スポーツの基本は「走る」こと。
この「走る」こと一つとっても色々な意味があります。
やみくもに走り込んでも効果が薄いどころか逆効果な場合もあるのです。

練習試合や合宿で、色々な学校の練習風景を見る機会があります。
そこで感じたのは、高校ラグビー界における「ランニングトレーニング」に対しての意識の低さ
もちろん、ちゃんと理解してメニューを組んでいるところはあります。
しかし、ごく僅かなのも事実。
アマチュアに限らず、トップの練習を見ていても
「どうして?」と思うことが実に多いのです。
例えば、みなさんは練習で「50mダッシュ×10本」「ポール間ダッシュ×10本」
といったメニューをやることがありませんか?
そのメニューに「何秒以内」というタイム制限がある場合も含めて。
でも、ちょっと考えてみてください。
なぜ本数は10本なのでしょうか?制限タイムは何を元に設定されたのでしょうか?
疑問に思ったことはありませんか?
私は「10」という数字、「設定されたタイム」の根拠が気になります。
指導者の方が何の目的で、
どのような効果を期待してそのトレーニング(本数、タイム)を取り入れたのか。
ある程度のスピードを維持して10本を楽に消化できる選手には効果が少ないでしょうし
そのスピードでは5本でバテてしまう選手にとっては、
さらに効果の少ないトレーニングになりかねません。
これは極端な表現になりますが「5本でバテる」ということは
「6本目以降は速いスピードを維持して走ることが難しくなる」ということですから
ジョグのような有酸素運動、つまり「自転車を漕いでいるのと変わらないくらいのレベル」
になってしまう。
10本を走れる選手と5本しか走れない選手では「違うトレーニング」になってしまうんです。
本数やタイムより大事なのは内容、根拠です。
そもそも選手全員が同じ本数を行うこと自体が非効率的。
走力に個人差があるわけですから、いくつかのグループに分けるべきでしょう。
それから不思議に思うのが、組分けをしていても
「レギュラー組と控え組」といった具合に野球の能力で決めること。
なぜ走力に合わせた班分けをしないのか?
ラグビーが下手でもしっかりメニューを走りきれる選手もいるわけです。
その選手にとってはそれがモチベーションにもなるし、
レギュラーを脅かす控え選手が出てくるはずです。
選手が行うトレーニングの数と同数の根拠がなければ練習は成り立ちませんし、
競技力の向上や期待する効果を手にすることは難しいでしょう。
スポーツの基本は「走る」こと。
この「走る」こと一つとっても色々な意味があります。
やみくもに走り込んでも効果が薄いどころか逆効果な場合もあるのです。

練習試合や合宿で、色々な学校の練習風景を見る機会があります。
そこで感じたのは、高校ラグビー界における「ランニングトレーニング」に対しての意識の低さ
もちろん、ちゃんと理解してメニューを組んでいるところはあります。
しかし、ごく僅かなのも事実。
アマチュアに限らず、トップの練習を見ていても
「どうして?」と思うことが実に多いのです。
例えば、みなさんは練習で「50mダッシュ×10本」「ポール間ダッシュ×10本」
といったメニューをやることがありませんか?
そのメニューに「何秒以内」というタイム制限がある場合も含めて。
でも、ちょっと考えてみてください。
なぜ本数は10本なのでしょうか?制限タイムは何を元に設定されたのでしょうか?
疑問に思ったことはありませんか?
私は「10」という数字、「設定されたタイム」の根拠が気になります。
指導者の方が何の目的で、
どのような効果を期待してそのトレーニング(本数、タイム)を取り入れたのか。
ある程度のスピードを維持して10本を楽に消化できる選手には効果が少ないでしょうし
そのスピードでは5本でバテてしまう選手にとっては、
さらに効果の少ないトレーニングになりかねません。
これは極端な表現になりますが「5本でバテる」ということは
「6本目以降は速いスピードを維持して走ることが難しくなる」ということですから
ジョグのような有酸素運動、つまり「自転車を漕いでいるのと変わらないくらいのレベル」
になってしまう。
10本を走れる選手と5本しか走れない選手では「違うトレーニング」になってしまうんです。
本数やタイムより大事なのは内容、根拠です。
そもそも選手全員が同じ本数を行うこと自体が非効率的。
走力に個人差があるわけですから、いくつかのグループに分けるべきでしょう。
それから不思議に思うのが、組分けをしていても
「レギュラー組と控え組」といった具合に野球の能力で決めること。
なぜ走力に合わせた班分けをしないのか?
ラグビーが下手でもしっかりメニューを走りきれる選手もいるわけです。
その選手にとってはそれがモチベーションにもなるし、
レギュラーを脅かす控え選手が出てくるはずです。
選手が行うトレーニングの数と同数の根拠がなければ練習は成り立ちませんし、
競技力の向上や期待する効果を手にすることは難しいでしょう。
Posted by hamakorfc at 13:36│Comments(0)
│管理人のつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。