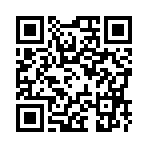2010年07月16日
チーム一丸

高校3年生にとっては、人生に一度しかない“最後の夏”がやってくる。
この夏をどう過ごすかでそのチームの「秋」が決まると言っても過言ではない。
また、メンバー選考へ向け、最後のアピール時期でもある。
大会でのベンチ入り総数は25名。
これからは、その定数を掛け、張りつめた緊張感の中での戦いを余儀なくされている。
最後の力を振り絞って一生懸命にラグビーに打ちこむ姿勢は、結果はどうであれ
人生を生きていく上での貴重な時間である。
それでも、やってくる。
メンバー発表という「一大事」が。
大会を戦う上で重要なのは「誰がメンバーになったか」だけではない。
メンバーが決まった後にこそ、それぞれのチーム力が試されるのだ。
花園予選を戦うメンバーと、そこから漏れた選手たちが、いかに気持ちを一つにできるか。
そこに、高校ラグビーにおける一番大切なモノが存在するのではないか。と私は思っている。
「チーム一丸となって闘う。」
選手たちは声をそろえて言う。
非常に聞こえのいい言葉だが、大事なのは、その意味がどこにあるのか?である。
試合に出ている選手が、誰か一人の力で戦うのではなく
つなぎのラグビーに徹することが「チーム一丸」なのか。
出場している選手が気持よく戦うための環境をベンチにいる選手が作ることが
「チーム一丸」なのか。
メンバーに入っている選手たちだけでなく、部員全員が同じ方向を向くのが「チーム一丸」なのか。
捉え方で意味が違ってくる。
「レギュラーになって、一生懸命やる。ベンチに入って一生懸命に声を出すんは当たり前のこと。
レギュラーに外れた中でも、一生懸命やれるかどうか。
教員の一人として、お前たちの姿を見ているからな。」
そう話しているのは、毎年、花園へ出場している某、高校の監督さん。
この高校は「チーム一丸」という部訓のもとに動いている。
それが定着してくるまでには時間がかかったというが、
その意味を理解してからというもの、チームは変わり始めた。
たとえば、試合中の裏方作業にしても、その一端は見える。
通常、レギュラーは公式戦の場合、試合に専念する為に
試合中の給水係やボールボーイを手伝う事はなく
試合に出場していない控え部員がやることになる。
それは、どのチームにも共通していると思うが、そんな状況下でも控え部員たちに
「ありがとう」と一声でも掛けているチームには、実力以上の力があると感じることができる。
一つの方向を向いているな、と。
とはいえ、こうしたメンバー外や控えの行動は、
例えば大会前の指導者の誘導でできるものではない。
日ごろからのチーム運営であったり、もっといえば、メンバー外の人間性に寄るところもある。
ある人から、こんなことを指摘されたことがある。
「メンバーから漏れて、ナニクソ!って思うことがそんなに悪いことなの?
普通の人間の感情じゃないか。そこを否定するべきではない。
実際、ある高校のメンバー外の選手で、『外れたからチームには勝ってほしくない』
というのをいっているのを聞いた。『応援なんかしたくねぇ』って。悪くないことだよ。
気持ちを一つにするとか、話しをつくりすぎじゃないか?」
一つの意見としては、分からないでもなかった。
しかし、こうも思うのだ。
3年間、メンバー入りを目指し、それが果たせなかったことだけで、
その選手の高校ラグビーは終わりなのかと。
メンバーに入れなかったら、それまでの努力が水の泡になるのか?と。
決してそうではないはずだ。
人生に「勝ち組」「負け組」を作って、閉そく感いっぱいの現代社会と同じように、
高校ラグビーを捉えても良いのかと思うのだ。
人生はまだまだ続いていくのだ。
最後の夏にメンバー入りできなかったことは、その当時では忸怩たる想いがするだろうが、
そこで人生のすべてが決まるわけではない。
むしろ、そこでレギュラーになったあまりに、プライドが邪魔をして、
その後、消えて行った選手を何人も見ている。
あくまで、「高校3年生の秋」限定で、メンバーから外れただけなのである。
それからの人生はまだ築いていける。
その忸怩たる思いを抱えながらチームのために、一生懸命尽くすことこそ、
優れた人間力を構築できるのではないだろうか。
「チーム一丸」の意味を問いたい。
先日、サッカーW杯がスペインの初優勝で幕を閉じた。
日本は初戦で、抜群のまとまりを見せて、カメルーンを破った。
その戦いぶりの良し悪しは他の方に任せるとして、私が一番印象に残ったのは、
予選まではエースと言われた存在だった中村俊輔が、
途中で交代して退いてきた選手に上着を渡していたシーンを見た時だ。
これが全員でやるということなのだ。
指揮官の戦術が上手くハマっただけではない。無形の力が作用したのだ。
だから、初戦に彼らは勝てた。私はそう思っている。
メンバー外の存在なくして、チーム力は上がらない。
これから夏合宿を経て、どのチームも強くなる。
自分たちだけ飛躍的に技術力が上がるかと言うと、そう多くは期待できないだろう。
その中で上がるとしたら、部員全員の気持ちを一つにすることで生まれる、プラスアルファだ。
「チーム一丸」という言葉の真の意味を大会までに、もう一度、考え直してほしい。
その意味が分かれば、必ず力になるはずだ。
この秋の戦いだけではなく、その後の人生にも、必ず生きる。
高校ラガーには、そのことを実践してほしい。
メンバーに外れて頑張れる人間こそ、本物のラグビーマンである。
タグ :浜工ラグビー部
Posted by hamakorfc at 08:15│Comments(0)
│管理人のつぶやき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。